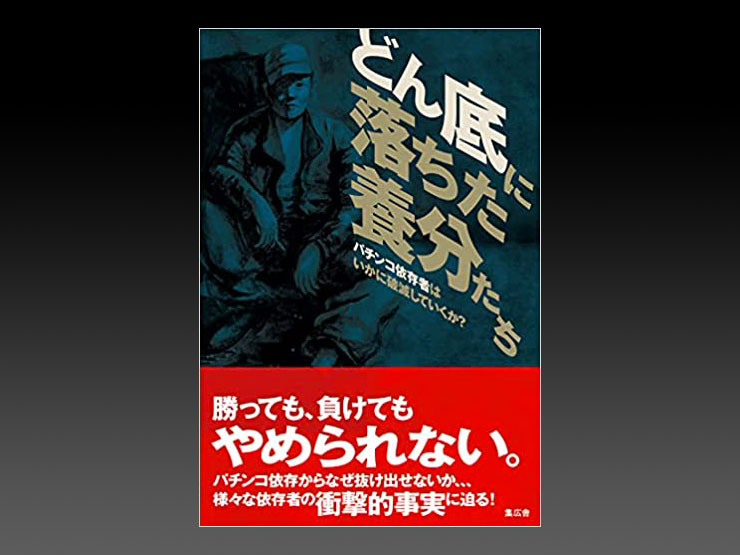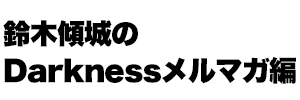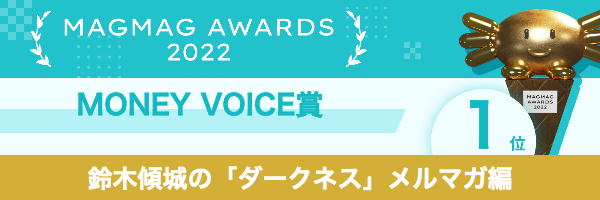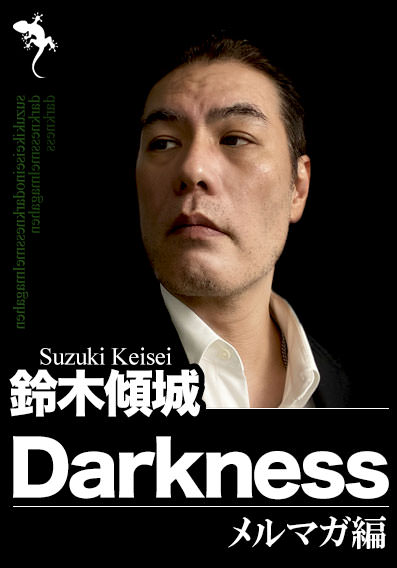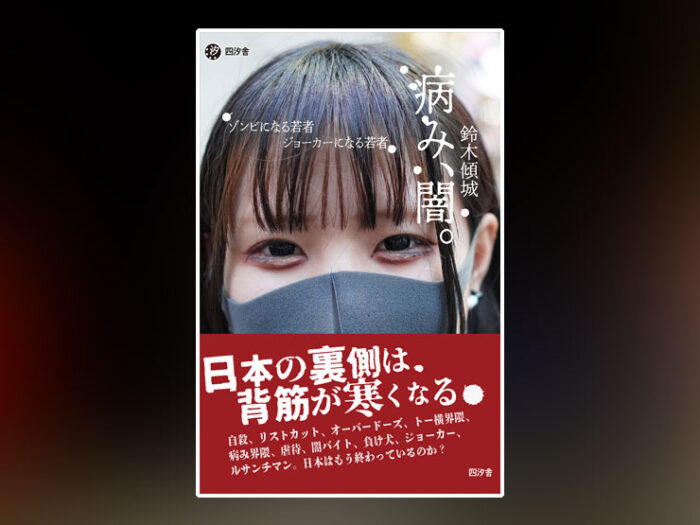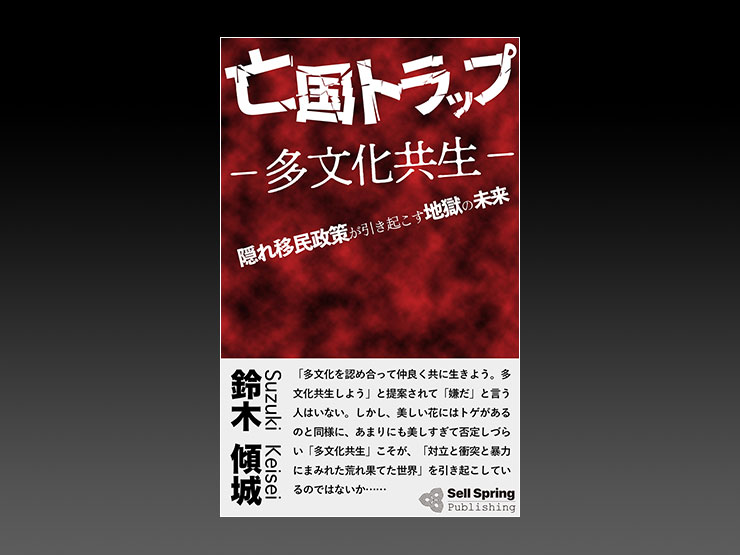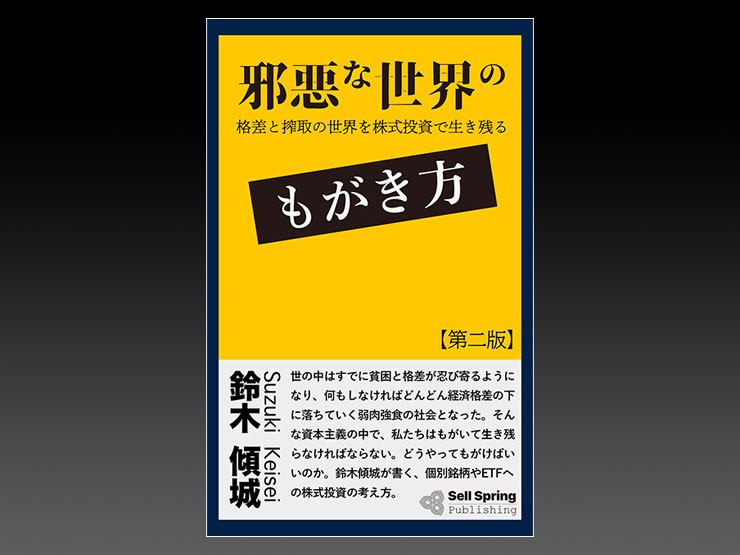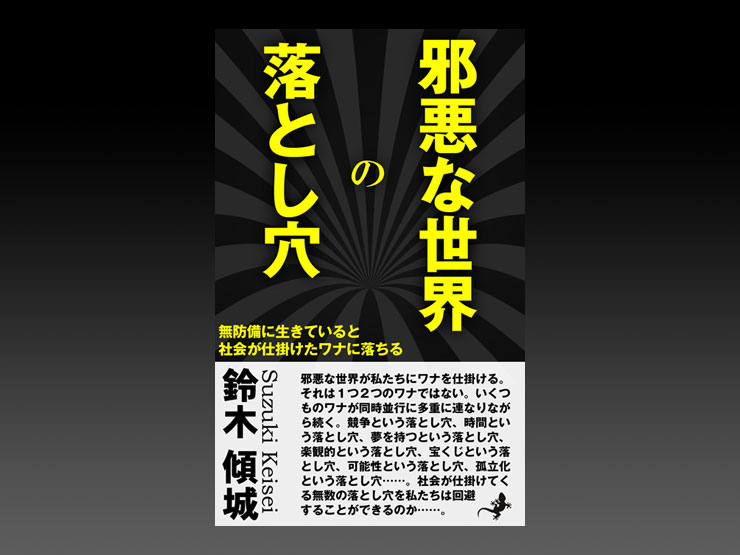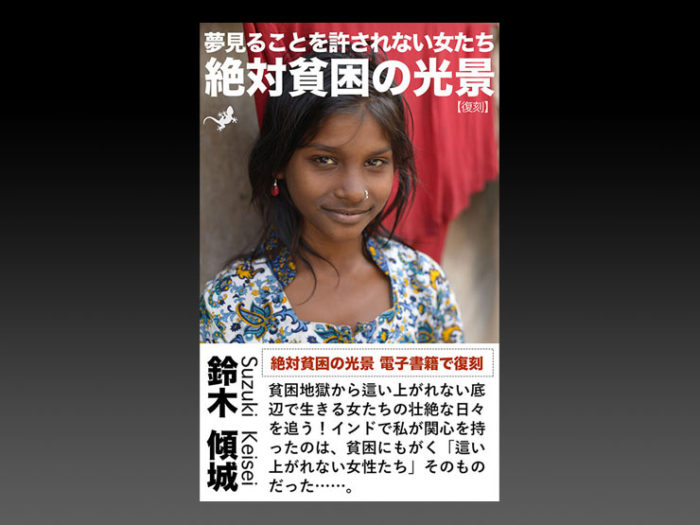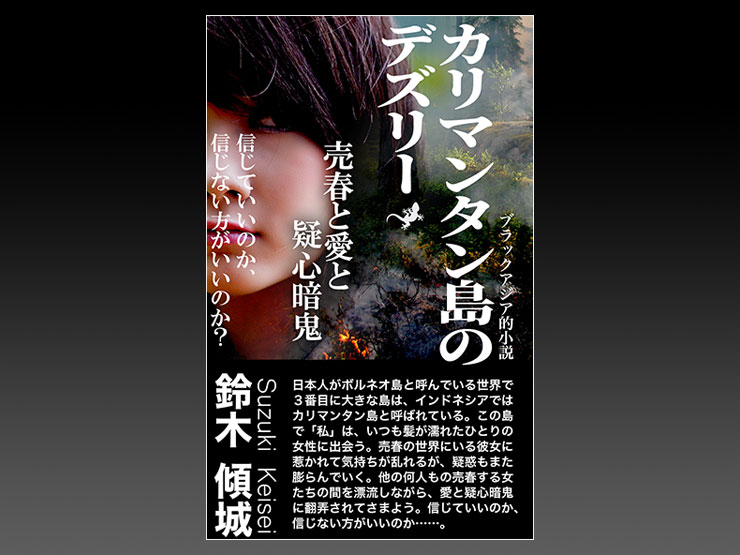プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019メディア『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
マネーボイスで私が寄稿している文章は、主に「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を中心に抜粋されたり、描き下ろししたりしているものです。この記事は『鈴木傾城のダークネス・メルマガ編』の記事のひとつです。ご関心のある方、どうぞメルマガにご登録下さい。
鈴木傾城 – マネーボイス掲載記事一覧
鈴木傾城のダークネス・メルマガ編

「まぐまぐ大賞2019」マネーボイス賞1位に選ばれたメルマガです。この記事はメルマガにて発行され、メルマガにて全文を読むことができます。1週間に1度、日曜日にメルマガでの発行を行っております。

まぐまぐ大賞2022 マネーボイス賞1位
週に一回、『鈴木傾城のダークネス・メルマガ編』をまぐまぐ!から発行しております。今年も、『メルマガの日本一はあなたが決める!まぐまぐ大賞2022 MAGMAG AWARDS 2022』の中で、まぐまぐメディア・マネーボイス賞1位を頂きました。2019年1位、2020年1位、2021年2位、そして2022年1位です。皆様に感謝します。
ダークネス・メルマガ編バックナンバー
ダークネス・メルマガ編は、バックナンバーも充実しております。たとえば、以下のようなバックナンバーが揃っております。
- 株主に報いる優良企業を保有するだけで金が金を連れてくる
- ロックフェラーの資産が陰謀も裏工作もなく増え続ける理由
- 弱肉強食の世界で自分が弱者だと気付いたらどうすべきか?
- 「現代資本主義の魔術」を身につける絶好の機会を見逃すな
- これで「無限にキャッシュを生み出すマシーン」が手に入る
- 次に押さえたいのは「変わりゆくものをすべて飲み込むこと」
- 少子高齢化と人口減で活力が低下する国がインフレにならないとでも?
- 資本主義では自分に才能がなくても、他人の才能を保有するのが基本だ
- 学歴を裏口で手に入れなくても「これ」でイージーモードに入れる
- 資本主義の中で、普通の人間が合法的に他人を搾取する方法がある
- 学歴・職歴・容姿・能力・年齢を超越して、旨味を吸う生き方を選べ
- 自分に投機の才能がないと分かっても、悪賢く立ち回る方法がある
- 「自分が働いて稼ぐ」という発想をするな。もっと重要な発想がある
- 「一生カネに困らなくなるための生き方」として第一歩を踏み出すために
- 「自分は努力しない」という生き方を、合理的に実践する方法を学ぶべき
読みたいバックナンバーはありませんか? 他にも大量のバックナンバーを満載してお待ちしております。
ダークネス・メルマガ編が生んだ電子書籍