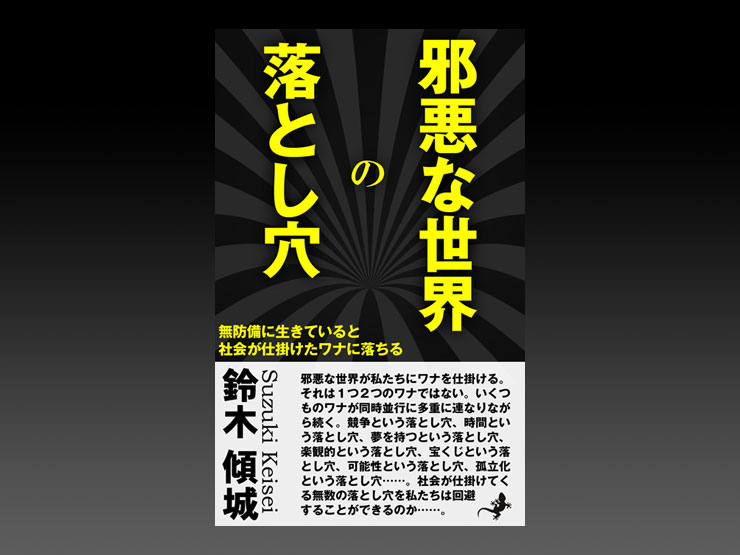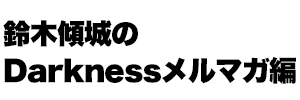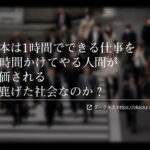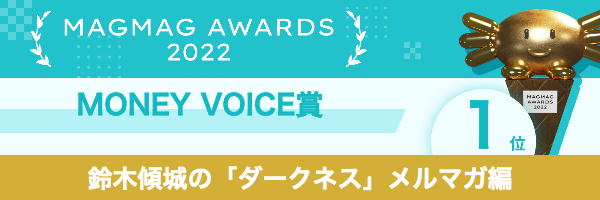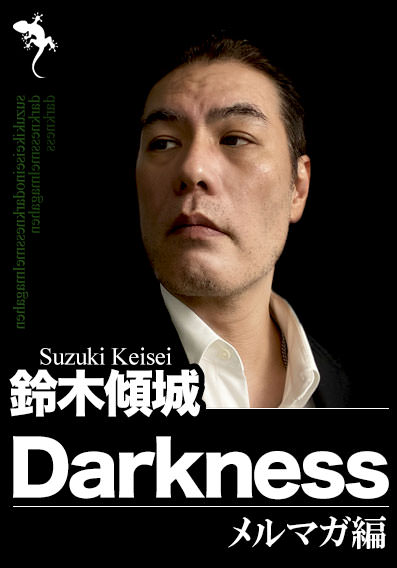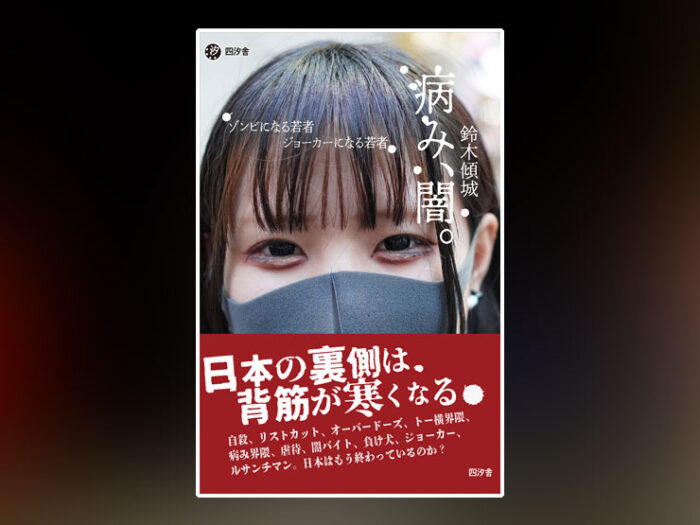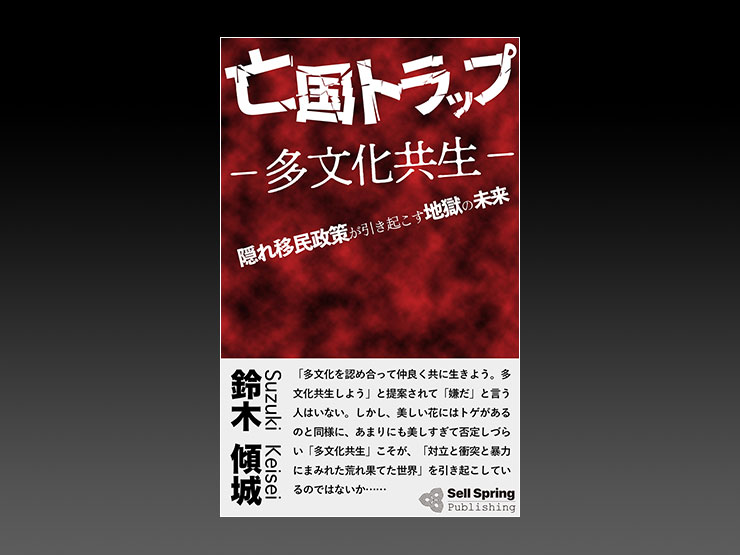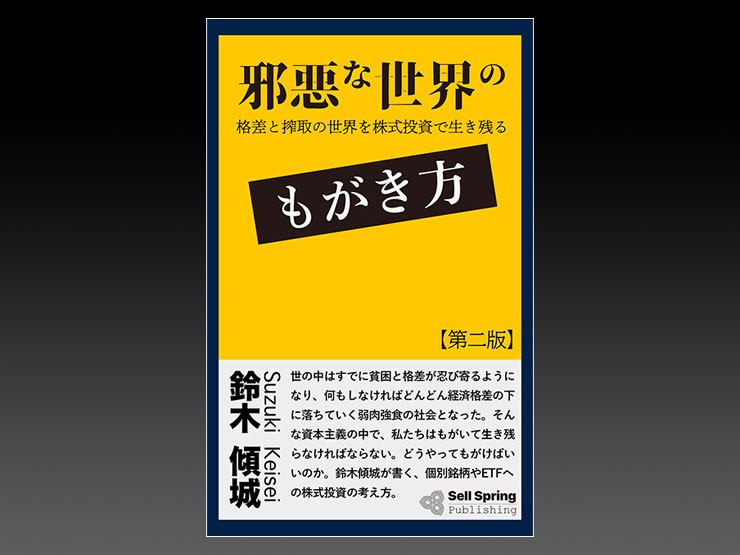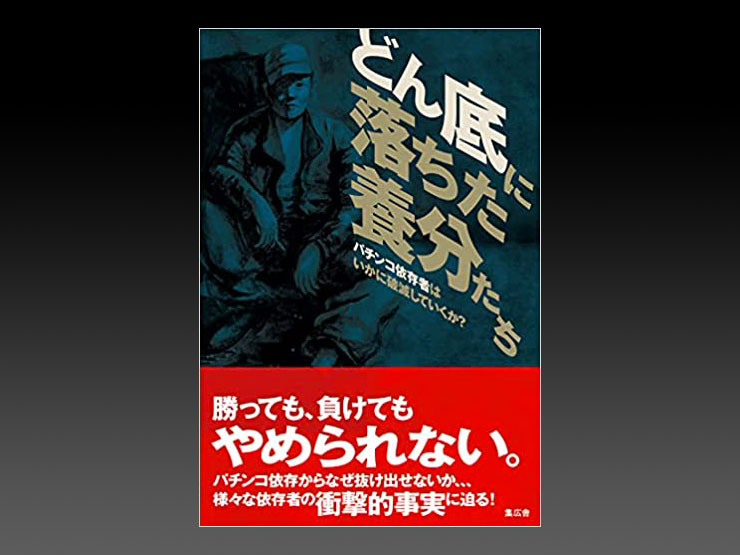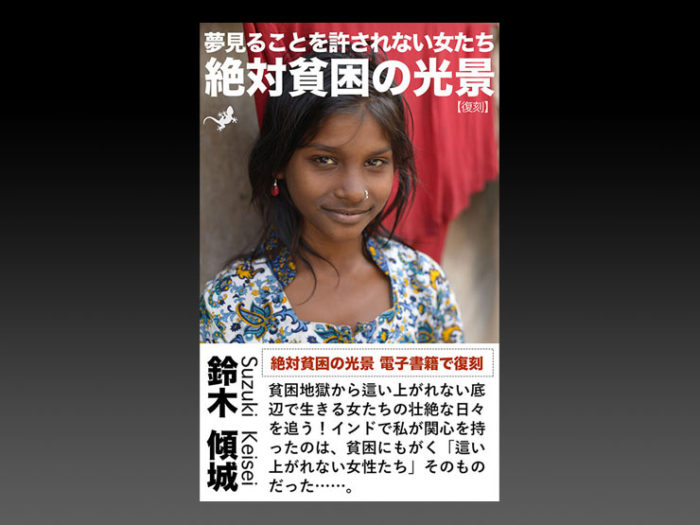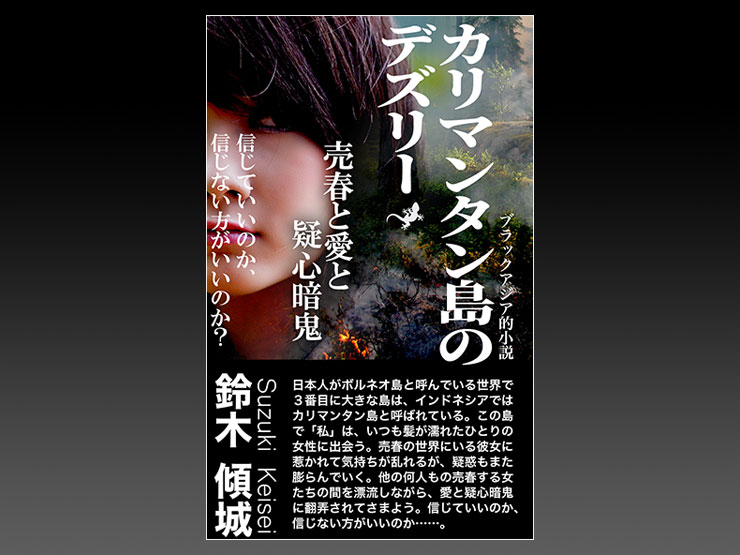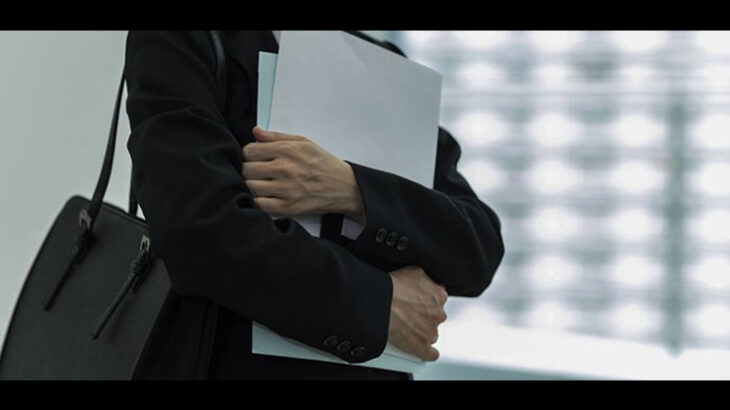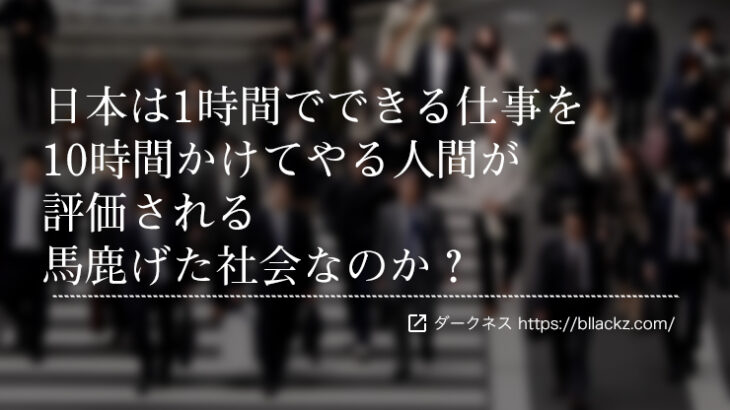多くの人は薄々気付いていても、気付かないふりをしていることがある。それは、資本主義社会の中では人間すらも「商品」だという事実だ。人材派遣の会社にとっては派遣する人間はまさに「商品」以外の何者でもない。だから「人間」派遣会社ではなく、「人材」派遣会社なのである。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
「人間もまた商品」という事実がここにある
いつの間にか日本に定着した働き方がある。それは「人材派遣」というものである。そして、派遣業務に携わる企業は「人材派遣会社」と言う。
彼らは「人間」を派遣しているのではなく、「人材」を派遣しているというのだが、その微妙な違いを私たちはよく考えなければならない。
多くの人は薄々気付いていても、気付かないふりをしていることがある。それは、資本主義社会の中では人間すらも「商品」だという事実だ。人材派遣の会社にとっては派遣する人間はまさに「商品」以外の何者でもない。
今の先進国社会の中では、多くの若者が大学に行く。文部科学省のデータでは、2019年度の大学・短大進学率は58.1%で過去最高となっている。しかし、大学には何のために行くのか、その意味を正確に把握している人はいない。
大学に行くのは、決して勉強して人間性を向上させるためではない。世の中の真理を究めるためでもない。自らの技能を追求するためもでない。もちろん、友達を作るためでもない。
本当の目的は何か。それは、大学を卒業することによって「自分自身の商品価値」を高めるためだ。要するに「学歴」のためである。
資本主義社会の総本山である企業は、社員を採用する際、どのような人間を選ぶのかの基準が必要だ。そこで、学歴を見る。学歴でその人間の価値がどれくらいのものなのかを知る。
これは、私たちが商品のスペックを見てどれかを選ぶのとまったく同じ発想である。企業も人間をスペックで判断し、誰を選ぶのか決めている。学歴は、「人材」として自分の商品価値を高めるためのスペックなのである。
だから、若者は大学に行き、自らの「商品価値」を必死で高める。良い悪いは別にして、資本主義の社会では「人間もまた商品」という事実がここにある。
【金融・経済・投資】鈴木傾城が発行する「ダークネス・メルマガ編」はこちら(初月無料)
歯車という部品化と、不良品という状態
学歴も、スキルも、保有する資格も、資本主義社会では「商品価値」を示すものであり、人間という商品のスペックを計るものなのだ。
サラリーマンは自分のことを「企業の歯車」であると自嘲することがよくある。この歯車というのは、自分が企業に役立つために買われた「歯車という商品」と言う現状を浮き彫りにしている。
歯車に人格はいらない。
歯車は会社が右と言えば右に回り、会社が左と言えば左に回るだけだ。これは、すなわち人間そのものが歯車という「商品」として企業に買われて、はめ込まれて使われているということを指している。
歯車になりたくないと叫んで、会社が右と言っているのに左に回っていたら「壊れている」と即、排除される。それは「不良品」だと呼ばれるのである。学校で勉強しない人間は「不良」と言われる。不良品と不良はよく似た言い回しだ。もちろん、これは偶然ではない。
商品:不良品
人間:不良
人間も資本主義社会の中では商品になっていると考えれば、この2つは同じものを指しているのも同様なのである。
学校の不良も、商品の不良品も、規格に合っていないという意味だ。それは、資本主義社会の役に立たない。だから、排除されるのだ。
会社は壊れている「不良品」を排除しても、別に困らない。なぜか。規格品は山のようにあるので、次はきちんとした規格品を買えば良いだけだからだ。
「代わりはいくらでもいる」というのは、人間そのものが商品化されているので、いくらでも「規格品を買える」という意味であることに気付く。
この規格化された人間のことを、私たちは「人材」と呼んでいる。「人材派遣会社」は人間を派遣しているのではなく、人材という規格化されたものを派遣している。知っていただろうか?
【ここでしか読めない!】『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』のバックナンバーの購入はこちらから。
それは、「商品化」されたという意味である
森の樹木は、その一本一本が生命である。しかし、資本主義社会では、その樹木を切り倒して規定の長さに切って、削って、商品化する。そうやって商品化された樹木は、もう生命体ではない。それは「木材」である。
規格に沿って商品化されることによって、樹木から材木という存在に変化したのだ。樹木が木材になったというのは、資本主義社会に組み込まれたということであり、それこそが「商品化」されたという意味なのである。
人間も同じだ。子供たち、若者たちの一人一人は個性があって、みんな違う才能、違う哲学を持っている。言ってみれば、バラバラだ。しかし、現代社会では、その人間を学校で規格化された教育をして個性を削ぎ落とし、平均化して、同質化する。
そうやって社会に送り出されると、みんなどこか似通った人間になっていく。「似通っている」というのが、まさに規格化された証拠なのである。そして、規格化された人間は、企業から「人材」と呼ばれるようになるのだ。
企業にとって、人間とは人材のことだ。材木と同じで、取り替えがいくらでも可能であり、「人材市場」でいくらでも規格に合ったものを買うことができる。つまり、「人材」とは規格化・商品化された人間のことである。
樹木:木材
人間:人材
こういった「規格品」を買って使うには金が必要だが、その人件費のことを企業は「コスト」と言う。コストとは費用のことだが、企業の中には社員を人材とも呼ばずにコストと呼ぶのだ。もう人間は、人材ですらもなく、単なる費用にされてしまっているのである。
人間=人材=費用(コスト)
言葉の変遷を見ても、どんどん「使い捨て」感が出てきていることが分かるはずだ。企業は、人材派遣会社から「人材」という商品を買って、それを「コスト扱い」として考える。
人材が「不良」だったら、新しいモノに取り替えてもらう。壊れても、新しいモノに取り替えてもらう。企業は「人材」でそれをやっている。
ダークネスの電子書籍版!『邪悪な世界の落とし穴: 無防備に生きていると社会が仕掛けたワナに落ちる=鈴木傾城』
私たちは「人材」として使い捨てにされる存在
私たちは誰もが資本主義社会の中で生きている。そのため、この「人間の商品化」から逃れるのは非常に難しい。どんなに抗っても、私たちは間違いなく資本主義の世の中で「商品化」されている。
結婚するときも、最近は相手を「婚活サイト」で選ぶ人も増えて来ている。ショッピングサイトで商品を選ぶように、婚活サイトで結婚相手を選ぶ。
そこでは「性格が良い」だけでは駄目で、どこの大学を出たのか、どこの企業に勤めているのか、年収はいくらなのかというスペック(属性)が重要になってくる。このスペックというのは、言ってみればその人の「商品価値」である。
スペックで人間を比較して選ぶ。要するに、結婚もまたショッピングと同じになった。まさに「人間の商品化」である。「好きだから一緒になる」という単純なものではなくなったのだ。
今の時代は「3組に1組が離婚」の時代だが、離婚や再婚が簡単なものになったのも、人間が商品化されているからで、「壊れたら捨て、新しい商品を買う」というのと同じ発想になっているからだ。
私たちは商品化されるし、私たち自身もまた他人を商品として見ることもある。それは、資本主義の世界で生きている限りはどうしようもないことなのかもしれない。
そうであれば、自分がどんな運命を辿るのかは、現代社会の中で、「商品」がどのように扱われているのかを見ればだいたい予測できる。
現在は、ひとつの商品を修理しながら大切に使う時代ではない。商品は使い捨てだ。これは、私たちもまた「人材」として使い捨てにされるということを示唆している。
現在は「何でも安ければ安いほど良い」という風潮で、誰もが100円ショップで何かを買う。これは私たち自身も「安い給料の人間であればあるほど良い」とコストで見られるということである。
私たちが商品を選ぶように私たち自身も選ばれる。私たちが商品を使い捨てにするように私たち自身も使い捨てにされる。商品の扱いが、そっくりそのまま人間の扱いになる。
人間も「人材」という商品として扱われているのだから、それは当然のことなのである。あなたは人間なのだろうか、それとも人材なのだろうか?