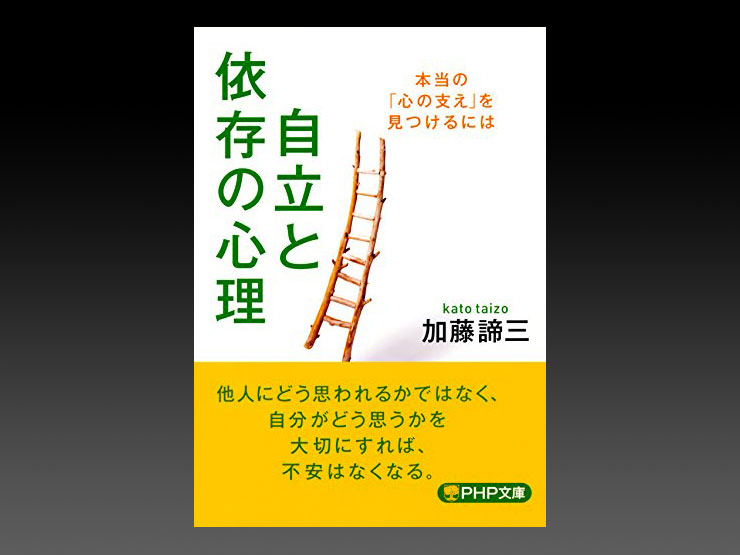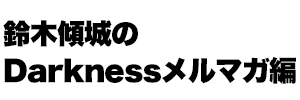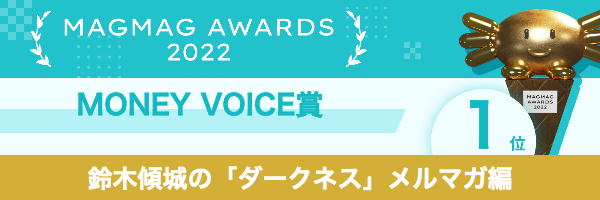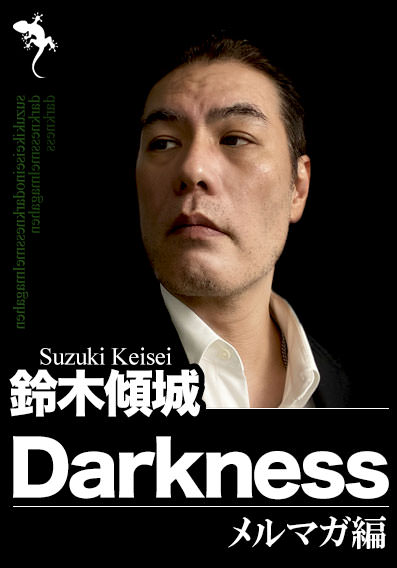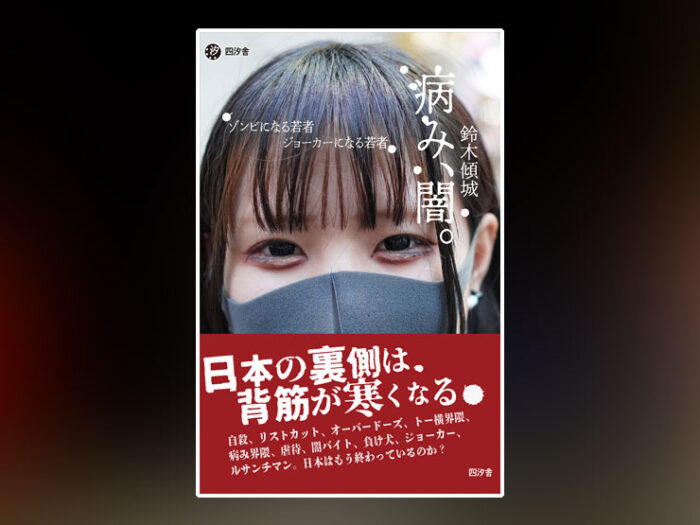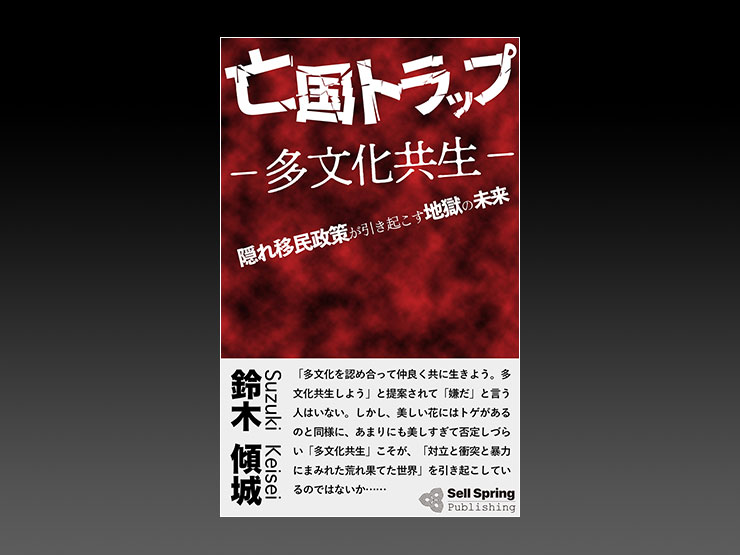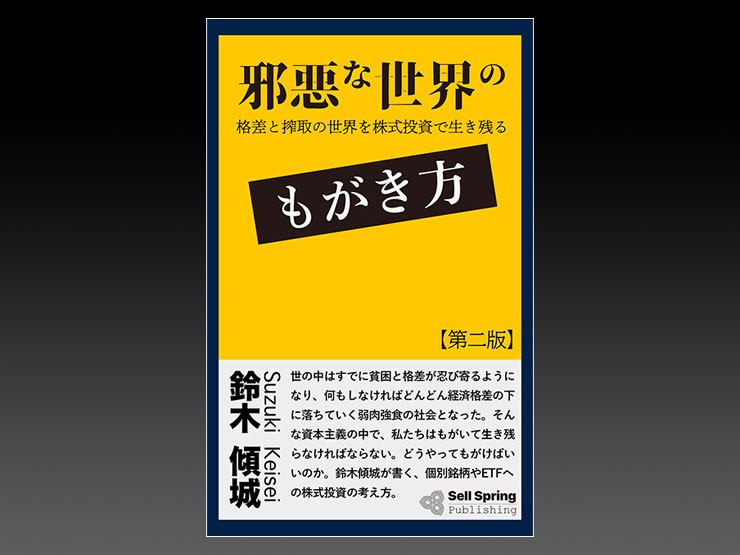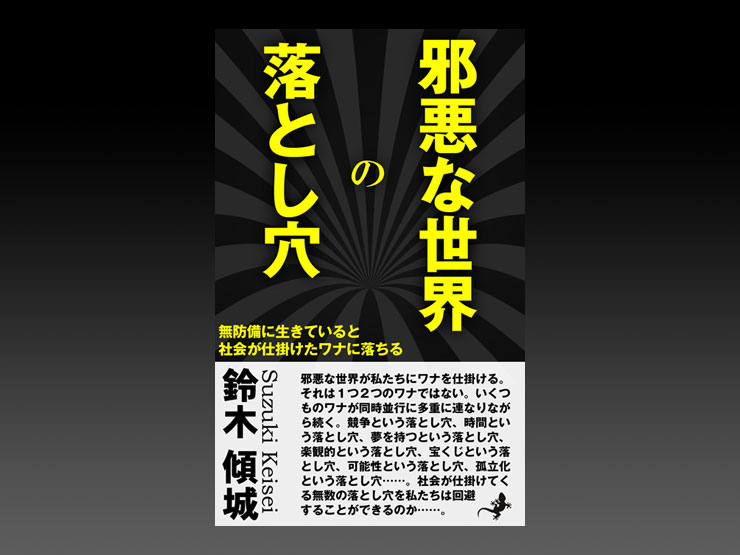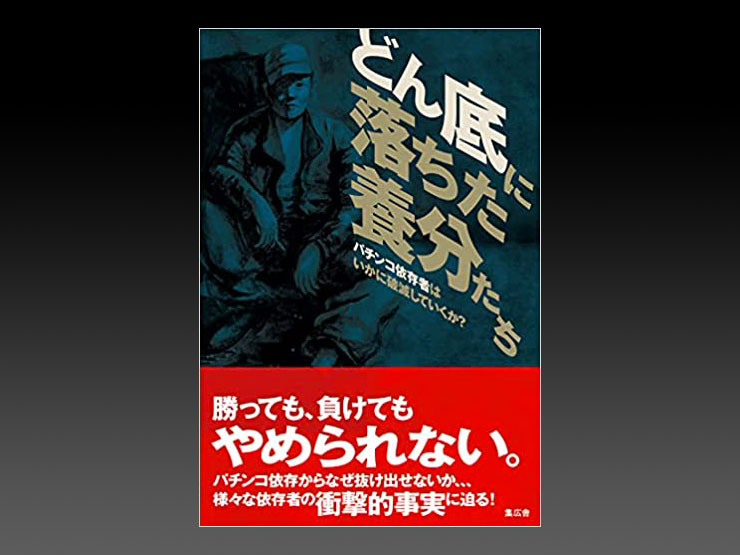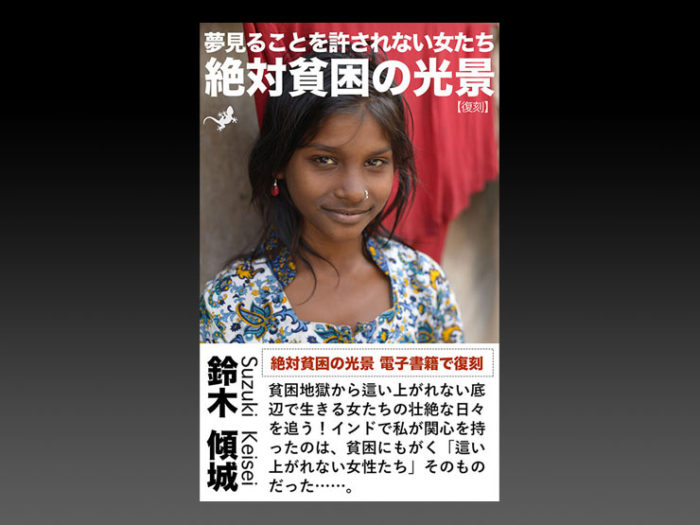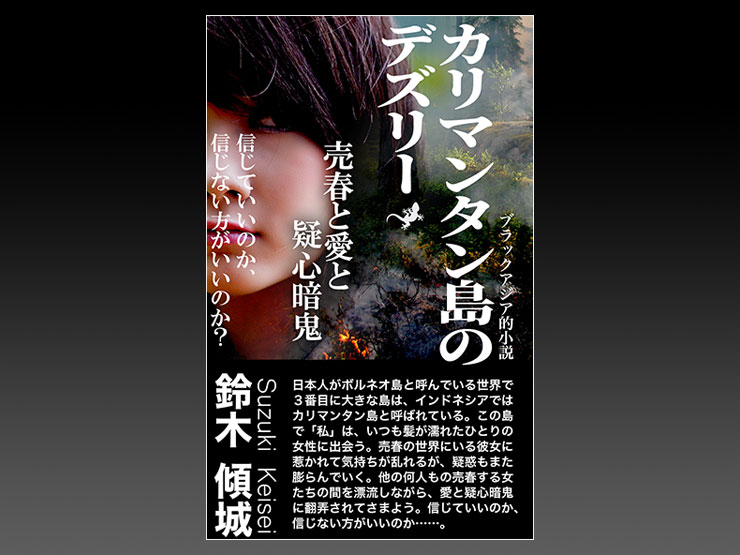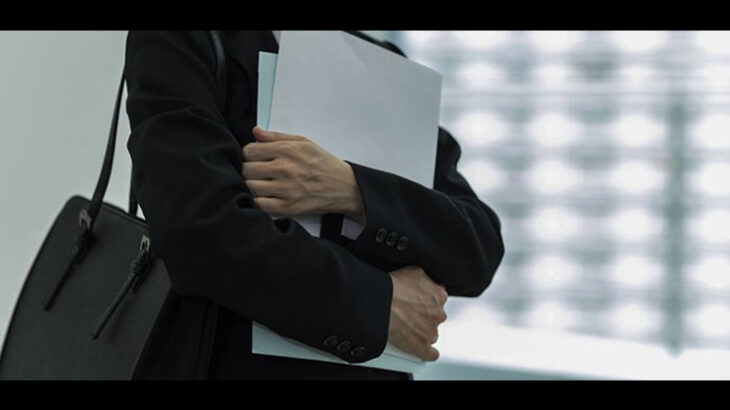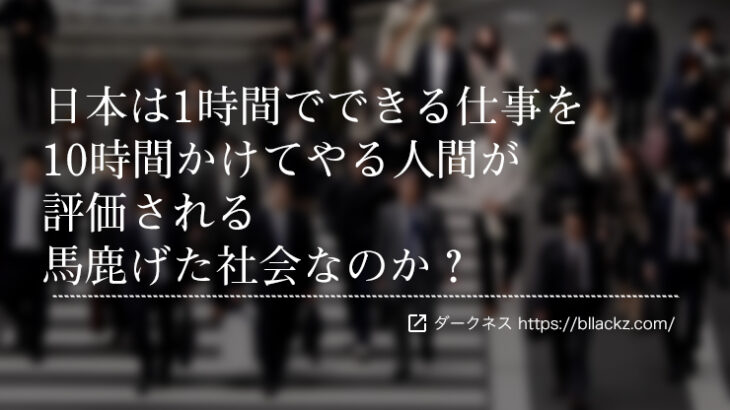高校や大学を卒業したら自動的に大人になれるわけではない。学校を卒業しても「誰か」に依存し、面倒を見てもらわなければ生きていけないというのであれば、まだ大人になっていないと見なされる。自立していなければならないのだ。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
「安月給の使い捨て雇用」を提案する企業
2020年は全日本人がコロナ禍で翻弄されたのだが、コロナ禍による不景気はじわじわと若年層を苦境に落としていく。不景気は求人数を減らし、学生の内定率を悪化させる要因となるからだ。
コロナ禍は2021年も持ち越されているわけで、長期に渡る不景気は2021年もボディーブローのように若年層を追い込む。
こうした若者の苦境を見て「月給16万円で2年間面倒を見てやる」と「安月給の使い捨て雇用」を提案する企業も出てくる始末だ。
就職が決まらないくらいなら、不利な条件でも仕方がないと、こうした足元を見て就活する学生を買い叩く企業に就職する学生もいるだろう。景気が良かろうが悪かろうが、とにかく社会に出て自分で生活を成り立たさなければならないからだ。
自分の人生を生きるには、誰でも親の家から出て行き、自分の食べる分は自分で稼ぐしかない。何から何まで面倒を見てもらわなければならないのであれば、一人前だと見なされない。
もし、いろんな意味で「親」から離れられない境遇であるのなら、それは「親」に借りがある状態だ。自立していない。
確かに、今の時代は自立するが難しい時代でもある。コロナ禍の中では尚更だ。しかし、いつの時代でも、自立という大変なことをしなければならないのが人間であって、それから逃げていては真の意味で「大人」になれない。
高校や大学を卒業したら自動的に大人になれるわけではない。学校を卒業しても「誰か」に依存し、面倒を見てもらわなければ生きていけないというのであれば、まだ大人になっていないと見なされる。
自立していなければならないのだ。
【金融・経済・投資】鈴木傾城が発行する「ダークネス・メルマガ編」はこちら(初月無料)
働いても働いても豊かになれない苛酷な時代に
コロナ禍が落ち着いたら社会は生きやすくなるとは限らない。現代社会はますます生きにくい時代となっている。
その理由は何度も述べている通り、企業が明確に利益優先主義に向かうようになり、世の中全体が雇用を削減しようとしているからだ。
インターネットの発展、IT技術の進化、人工知能、ロボット化は、人々の娯楽になる一方、企業が雇用を排除するためのテクノロジーにもなっている。現在はクラウドの時代だが、クラウド化は様々なソフトウェアのサービスを生み出している。
クラウド上で動くソフトウェアサービスは「SaaS」と称されているが、メールはもちろんのこと、今やワープロも表計算も、すべてクラウド上で動いている。
従業員はクラウドで客とコミュニケーションし、クラウドで業務を完結し、クラウドで情報を共有する。
企業はこうしたテクノロジーを存分に使って効率化を推し進めた結果、今まで10人でやっていた仕事が5人で、5人でやっていた仕事が3人で、3人でやっていた仕事が1人でできるようになったのだ。
そうした効率化を成功させればさせるほど、企業は利益を上げられるので、これからの企業は「いかに人を雇わないで利益を上げるか」に邁進することになる。人を雇わなければ事務所も縮小できる。
皮肉なことに、コロナ禍はテレワークを急激に促進させていくことになったので、企業は逆に効率化をより広範囲に押し進めることができるようになったという側面もある。実際、2020年に入ってから効率化とテレワークで事務所を縮小した企業は多かった。
効率化が進めば進むほど、必然的に雇用も少なくて済むようになる。
だから人々は、少なくなっていく仕事口を求めて安い給料でも妥協して働くようになっていき、世界中でワーキングプアの人々が出現するようになった。「働いても働いても豊かになれない」という苛酷な時代になっていったのである。
しかも、どこかの会社に潜り込んでも、会社は一生面倒を見てくれるわけでもないので、会社に依存もできない。会社から放り出されたら「人生終わり」であれば、それもまた自立しているとは言えない。
【ここでしか読めない!】『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』のバックナンバーの購入はこちらから。
自立するというのは、「依存から抜け出すこと」
自立するというのは、「特定の誰かからの依存から抜け出すこと」と考えなければならない。「特定の誰か」からの依存から抜け出し、自分の力で生きていけるという状態にするのが「自立するという意味なのである。
20歳前後の若年層が依存しているのは、大抵が「親」だ。だから、彼らから見ると「親」の依存から抜け出してひとりで生きていくというのが自立である。
しかし、「親」の依存から抜け出して、どこかの「企業」に入ってその企業に隷属してしまうと、今度はその企業なしには生きていけない身となってしまう。
つまり今まで親に隷属していたのだが、今度は企業に隷属する形になる。隷属する対象が変わっただけで、これでは自立したとはとても言えない状況である。「特定の誰か」に隷属したままなのである。
何はともあれどこかの会社で働いていると、自分の食べる分は自分で稼いでいるという点で一応は自立していることにはなる。
親の家にしがみついて、ニートや引きこもりをしているような人間に比べるとずっとマシだ。しかし、それでも特定の企業に隷属するしか生きていけないのであれば、「自立している」とはとても言い難い。
どこかに隷属してしまうと、どんな理不尽を突きつけられても従うしかなくなる。
ブラック企業というのは、労働者を奴隷のように酷使する企業を指すが、その企業に隷属してしまっている人にとっては、そこに隷属するしか生きていけないと思っているので、どんなに酷使され、冷遇されても我慢するしかない。
そんな状況では自立しているとは言い難い。
今は無人島で暮らすような時代ではないので、人は誰でも誰かに依存しながら生きている。だから、自立するというのは「自分ひとりで何でもかんでもしなければならないこと」というわけではない。
自立するというのは、「特定の誰か」に頼らなくても生きていけるという意味である。特定の誰かとは、「親」かもしれないし「企業」かもしれない。そう考えると、「自立する」というのは学校を卒業したばかりの若者だけの課題ではないことに気付くはずだ。
ダークネスの電子書籍版!『邪悪な世界の落とし穴: 無防備に生きていると社会が仕掛けたワナに落ちる=鈴木傾城』
自立できていなければ社会のどん底で食い物にされる
「自立しているのか?」というのは、生きている全員が自分の人生に問いかけなければならない重要な問題である。引きこもりやニートの息子に「自立しろ」と怒鳴る父親も、実は特定の会社に依存して、そこから追い出されると生きていけない立場であるのであれば自立していない。
特定の誰かに依存し、隷属してしまうと、どんな理不尽を要求されても拒否できない。本当に自立していると、理不尽なことがあったら、すぐにそこから抜け出せる。自分の道を自分で切り拓いていける。自分のために頑張ることができる。
そう考えると、自分が自立できているのかどうかというのは、一生を通して自分に問いかけなければならないことであり、人生の目標ともなることなのだ。
誰かに隷属して生きているのであれば、自立していないのだと自分を分析しなければならない。自立は誰かが与えてくれるものではない。自分でつかむものである。自立できなければ自分の人生を生きるというのは到底できない。
しかも、自立できていなければ社会のどん底で食い物にされる。
「月給16万円で2年間面倒を見てやる」と「安月給の使い捨て雇用」を提案する企業というのはパソナである。パソナの会長である竹中平蔵は何と言ったか。
『正規雇用と言われるものは、ほとんどクビを切れないんですよ。クビを切れない社員なんて雇えないですよ、普通。それで非正規というのを、だんだんだんだん増やしていかざるを得なかった』
竹中平蔵は会社に依存する人間を「効率的に」切り捨てることができる非正規雇用者を増やした人物でもある。自立していない人間を「安月給の使い捨てできる要員」として捉えたのが竹中平蔵なのである。
こういう人間が弱肉強食の資本主義の頂点にいるのだから、いかに注意深く自立しておかなければならないのかが分かる。自立していなければ、食い物にされてしまうのである。