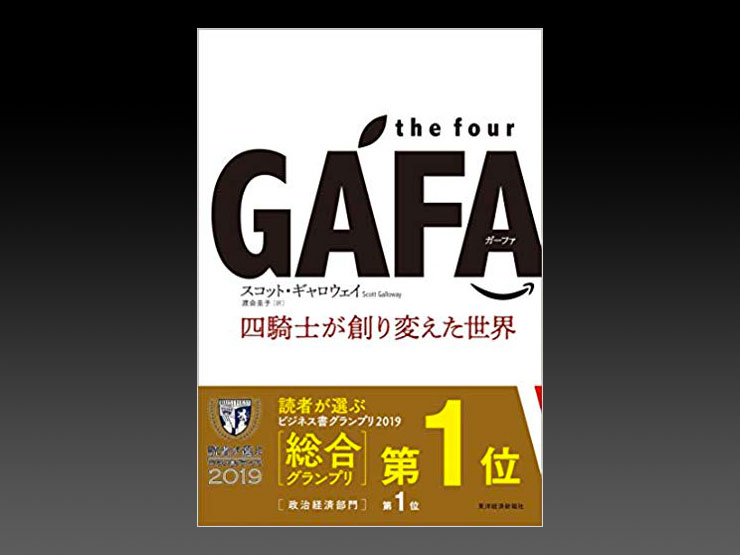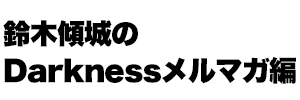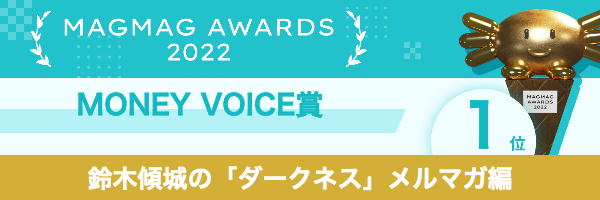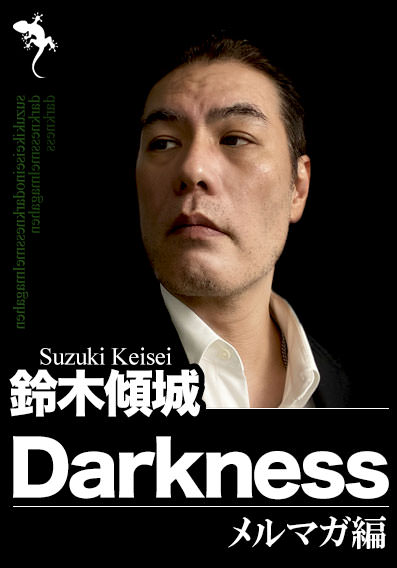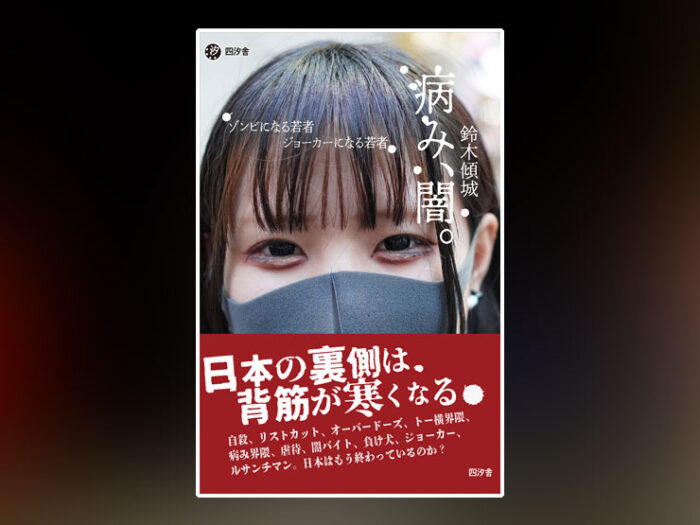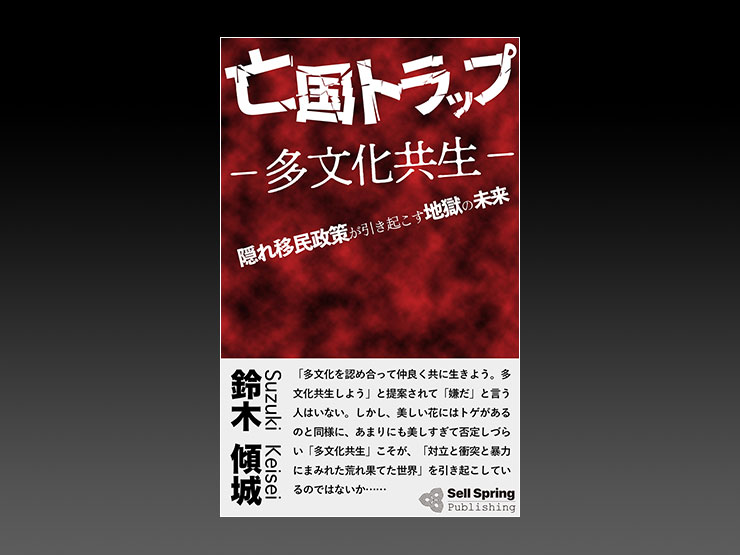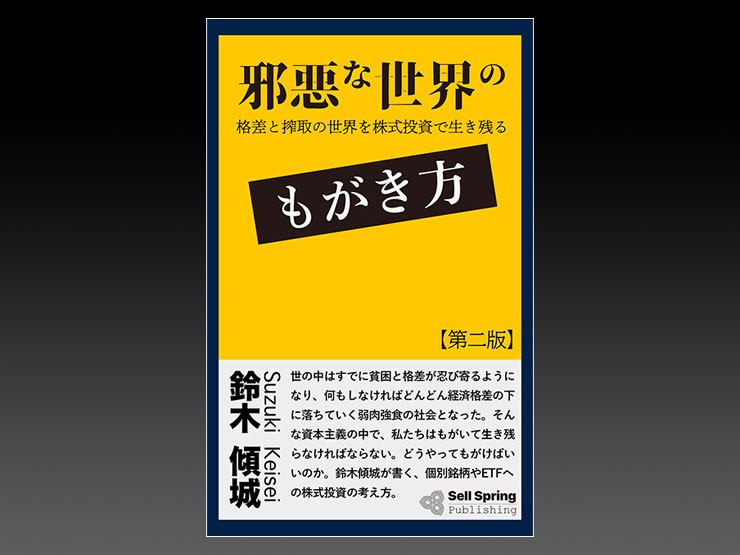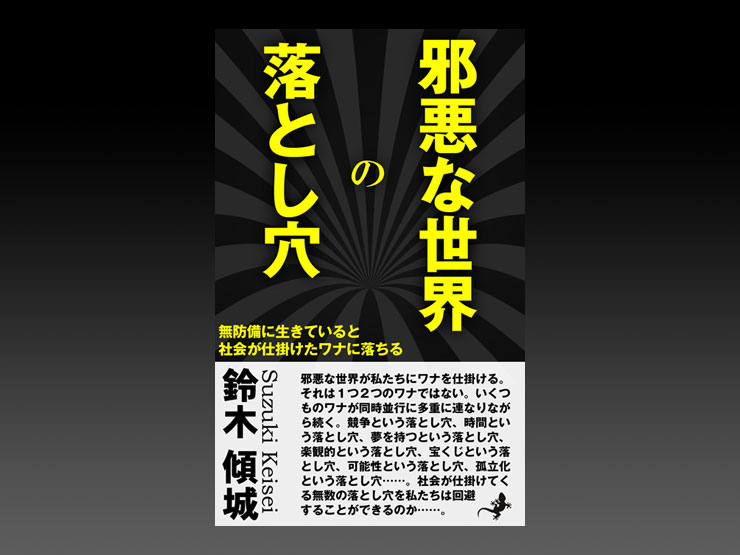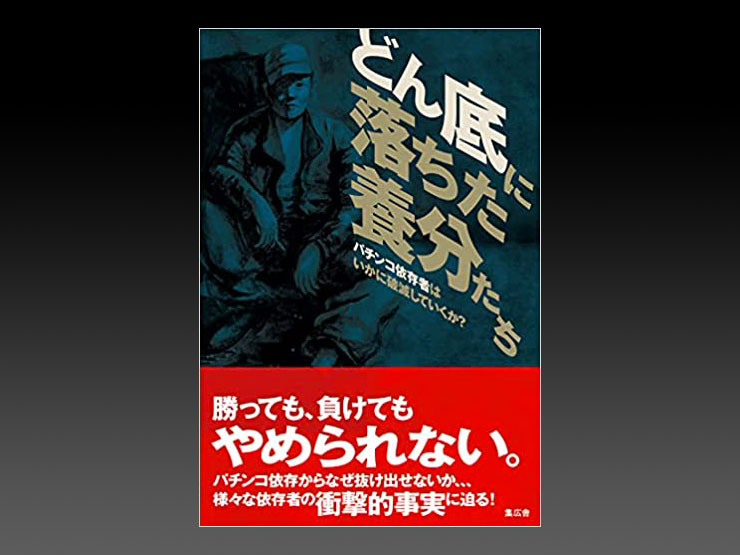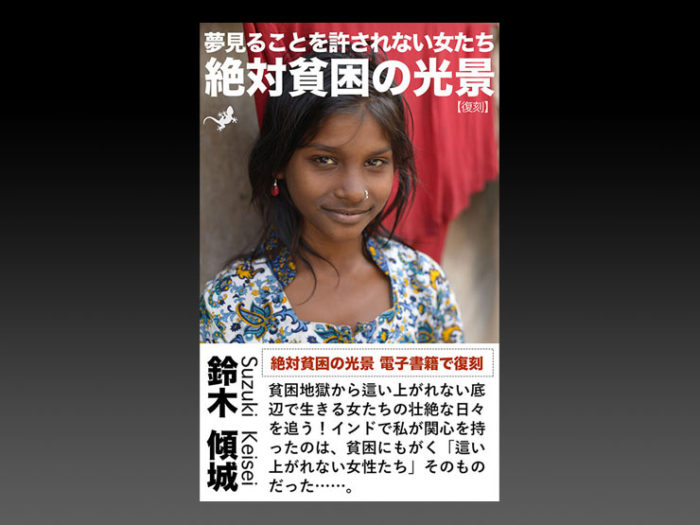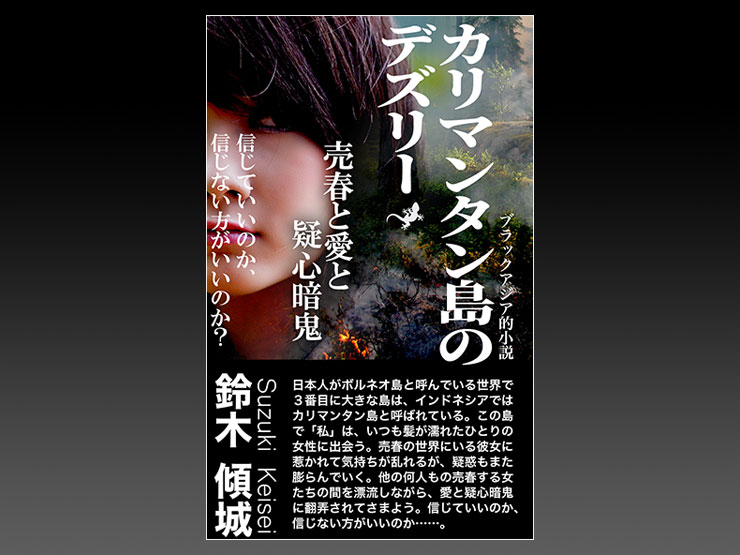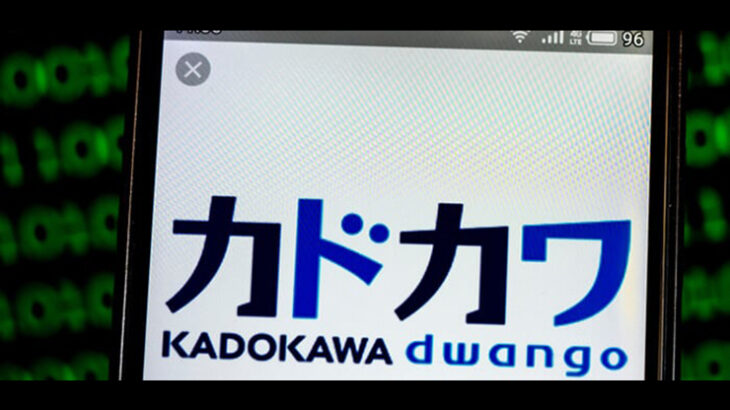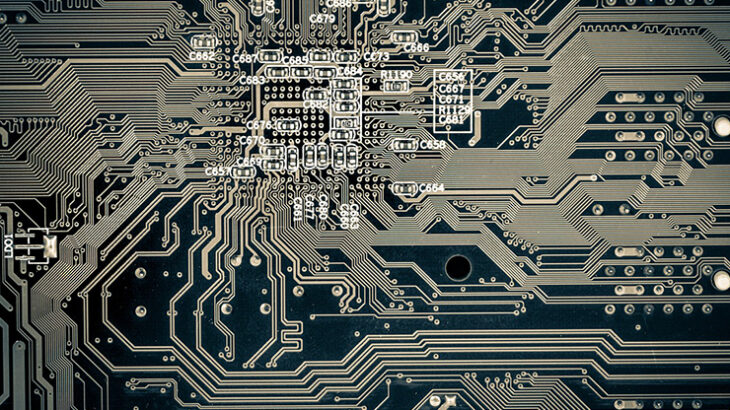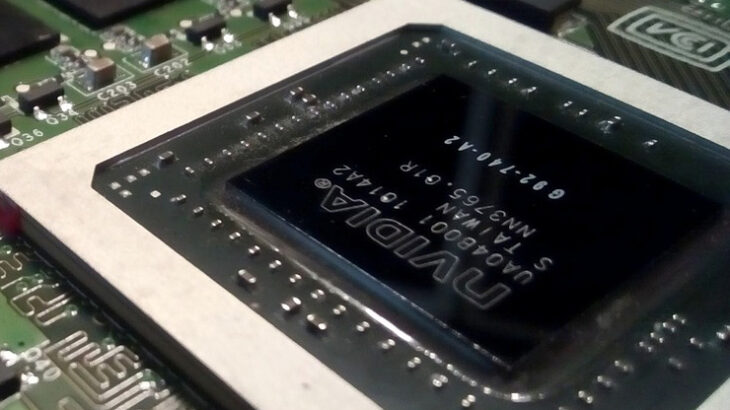テレビは自分たちが映したいものだけを映す。自分たちの都合の良いものだけを映す。都合の悪い意見や映像は決して見せない。偏向し、歪曲し、捏造する。そんなテレビ局の時代も終わった。もうインターネットが主流になり、テレビの時代に戻ることは決してない。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019、2020年2連覇で『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
YouTubeに進出した芸能人の方が逆に稼ぐようになった
これからテレビというオールドメディアは完全凋落して、インターネット全盛の時代に入るのは予測された未来である。このパラダイムシフトが起きたのは2019年であるというのは誰もが認めるところである。
2019年には何が起きたのか。この年、インターネット広告がテレビ広告を抜き去ったのである。
急激なデジタルシフトが起きており、視聴者は群れをなしてテレビからネットに拠点を移している。いまや若者はスマートフォンで動画を見ており、テレビを所有しない層も珍しくなくなった。
それに合わせてテレビ局も赤字を計上するようになっていき、2020年は在京民間放送局5社(日本テレビ放送網株式会社、株式会社テレビ朝日、株式会社TBSテレビ、株式会社テレビ東京、株式会社フジテレビジョン)のうち、テレビ東京をのぞくすべてが減益か赤字に転落するという事態に陥っている。
今後もテレビ広告は減少を止められない。制作費も削られてテレビはますます面白くなくなる。テレビ番組の質も悪くなっていく。番組の偏向もひどく、インターネットリサーチの調査ではテレビ局に対する信用はもう4割を下回っている。
テレビはすでに「オールドメディア」である。高齢者しか見ない。テレビ業界全体がこれから凋落していくのは決定的なのである。芸能人のテレビ離れも徐々に徐々に進んでおり、多くがYouTubeに活路を見出すようになっている。
テレビはすでに「絶対王者」ではなくなった。芸能人も「テレビに出ないと生きていけない」という世界ではない。早くからYouTubeに進出した芸能人の方が逆に稼ぐようになってきているのである。
【金融・経済・投資】鈴木傾城が発行する「ダークネス・メルマガ編」はこちら(初月無料)
テレビの凋落は、もう隠せないものになっている
映像を見てもらう媒体として、テレビ局は「寡占企業」でもあった。個人がテレビ局に挑戦を叩き付けるということはできなかった。だからテレビ局は今まで好きなように偏向報道もできていたし、好き勝手に世論を操作していたのである。
しかし時代は変わったのだ。インターネットではYouTubeを筆頭に多くの動画サイトが台頭するようになった。
ドラマにしてもNetflixなどが登場して日本にも定着するようになってきている。映画もYouTubeやAmazonやAppleやDisneyのチャンネルで見るのが当たり前になっているのである。
誰もが、自分の好きなものを好きな時間に好きなだけインターネットで見ることができるようになったのだ。
かつては「日常で気軽に映像を見たい」と思えば、テレビを見るしかなかったのだが、これからはテレビではなくインターネットが最初に選ばれるようになっている。
テレビは「見たいものをすぐに見る」というニーズに合っていない。映像を飛ばしたり巻き戻したりして「見たいものだけ見る」というニーズも満たしていない。つまり、時代遅れと言うしかないメディアになっている。
そして、テレビは自分たちが映したいものだけを映す。自分たちの都合の良いものだけを映す。都合の悪い意見や映像は決して見せない。偏向し、歪曲し、捏造する。
日本は言論の自由が守られているので、どんな意見があったとしても発言する機会は守られるべきだ。しかし、テレビ局は一方に偏った意見を世の中のすべてのように報道することができた。
自分たちの都合の良い方向に誘導する偏向報道の汚い手口は今も使われている。
【ここでしか読めない!】『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』のバックナンバーの購入はこちらから。
テレビ局はインターネットでは完全に無力だ
ところが、今や多くの人々がインターネットで情報を得て、そこにある「生の動画」でテレビが決して報道しない意見をも知るようになっている。テレビの世論誘導が意味をなくして影響力を急激に失っているのが今の時代である。
もちろん、これからもテレビ局という巨大メディアの影響力は突如として消失するものではない。いまだにその影響力は、計り知れないものがある。
しかし、多くのテレビ局が赤字転落し、テレビ局全体が信用されなくなっているのを見ても分かる通り、凋落は隠せないものとなっている。その影響力は徐々に減退している。
テレビには誰も逆らえないし、テレビの影響力を誰も凌駕できないと少し前の私たちは考えていたが、そんな時代はいよいよ終わろうとしているのだ。
今では自分で撮った映像はインターネットに流せば多くの人たちが見てくれるようになっている。人々やテレビ局の囲い込みから脱するようになったのだ。
見たいものだけを見る。何度も繰り返し見る。瞬時に検索で引き出して見る。世界中の人たちの動画を見る。マニアックだが自分が好きな動画を見る……。
こうした要望に、テレビは何ひとつ応えることができない。テレビは今の人々の要望に対応できていない。しかし、インターネットではそれが可能になっており、技術の進歩で映像の質もクオリティも上がってきている。
人々は見たいものを見る時代になっており、だからこそ要望に応えられないテレビが今後も寡占ビジネスでいることは絶対的に不可能なのだ。
ダークネスの電子書籍版!『邪悪な世界の落とし穴: 無防備に生きていると社会が仕掛けたワナに落ちる=鈴木傾城』
テレビ局がこれからもずっと君臨できるわけがない
テレビは決して消えることはない。しかし、ビジネスモデルはもう古臭く、業界は完全に縮小していく。必然的に、今までの強大なパワーは消える。テレビからインターネットへの転換が起きて、結果としてテレビ局の世論操作をする力も消えていく。
インターネットは全世界につながった巨大なネットワークであり、たかが日本のテレビ局ごときがすべてを支配しようとしても不可能なスケールである。日本のテレビ局が自分たちの都合の良いものだけ流れるように細工することなど最初からできない。
今までテレビ局は「放送免許」を盾にとって放映権をコントロールしていたが、インターネットでは最初からそれができないので、最後には「大勢の中の小さな存在」と化す。
インターネットの場合、人々は自分の見たいものを検索エンジンによって引き出すが、日本のテレビ局が自分たちの番組だけ検索に引っ掛かって、残りは引っ掛からないようにしたいと思ってもできない。
テレビ局はインターネットの前では無力だ。何もできない。「放送免許」にあぐらをかき、視聴者を囲い込んできたテレビ局はその環境をインターネットに奪われてしまった。だから、テレビ局の凋落はもう決定付けられている。
もうテレビ局のビジネスには未来がない。終わりだ。
インターネットで動画を配信するのに対してコストはかからない。自分の撮った、ちょっとしたビデオ動画をインターネットに載せて見てもらうのは、あきれるほど簡単にできてしまう。
それがどんな些細な動画であっても、それを面白いと思う人もいるし、実際に大量の視聴者が付く。インターネット時代では、何気なくアップしたさりげない動画でも、一瞬にして地球の裏側まで配信される。
そんな時代になっているのだから、下らない番組しか作る能力のないテレビ局がいつまでも世の中に君臨できると思う方がどうかしている。
【マネーボイス】読むと世の中がクリアに見える。鈴木傾城の経済を中心とした必読の記事がここに集積。
この際、私たちはみんなでテレビを捨てればいい
物量でもテレビはもうインターネットに適わない。テレビ局が24時間ぶっ通しで何かを放映したとしても、その間にインターネットの動画サイトでは、テレビを上回る莫大な数の動画がアップされる。
しかもインターネットでは、ストック能力が無尽蔵であり、テレビのように「過去のものが見られない」という欠点はない。むしろ、過去のものがいつでも見られるのがインターネットの大きな利点なのだ。
たしかにネットに散乱するコンテンツは、玉石混淆の状況だ。しかし、テレビ局はそれを批判することはできない。なぜなら、テレビ局が見せるコンテンツも玉石混淆だからだ。
さらに言えば、視聴者もみんな玉石混淆だ。だから、ありとあらゆるタイプのコンテンツが膨大に提供されるネットの方が、完全に優位にあるのは間違いない。
こんな中でテレビ局は生き残れるのだろうか。もちろん、生き残るだろうが、その影響力は完全に喪失して斜陽産業と化す。それは、テレビ局の人間が一番よく知っているはずだ。
下らない世論操作をしていると、それだけ視聴者に見捨てられるのが早まるだけだ。どの角度から見ても、すでにテレビ局の時代は終わっているのだから、偏向を隠そうともしないで世論操作をしまくっているコメンテーターも、一緒に終わるだろう。
放置しておけばいいのだが、意図的にテレビの時代を「早く」終わらせるためには、私たちがこれから意図的にテレビを見ないようにすることに尽きる。
そう言えば、NHKは「NHKが映らないテレビでも受信料を払え」と言ってきているので、この際、私たちはみんなでテレビを捨てればいい。