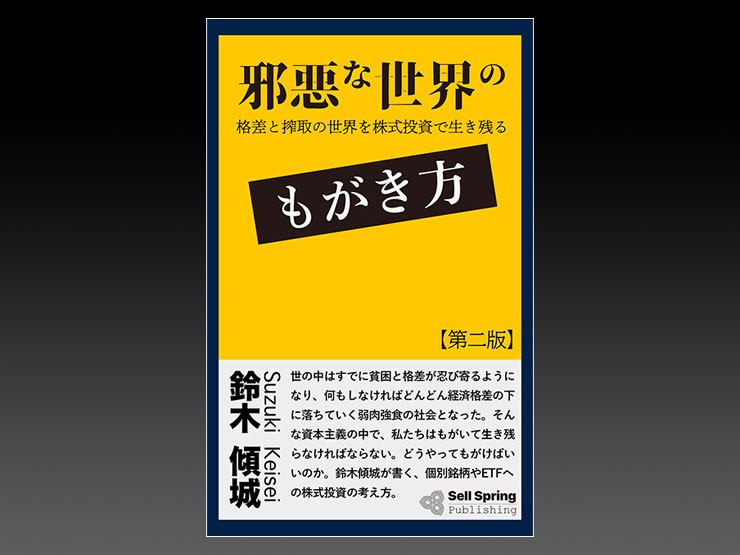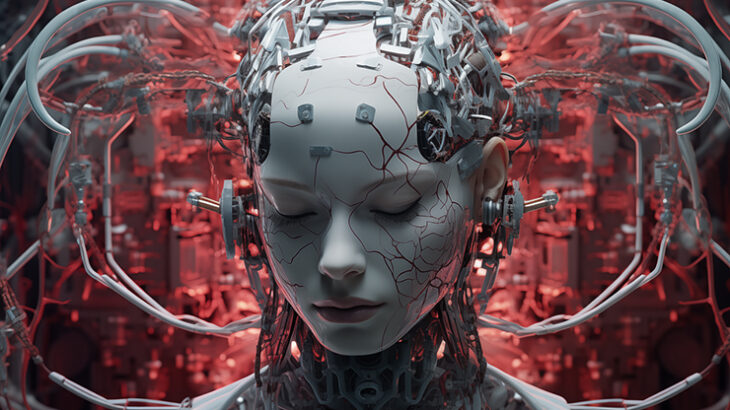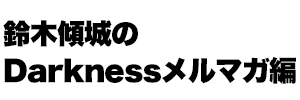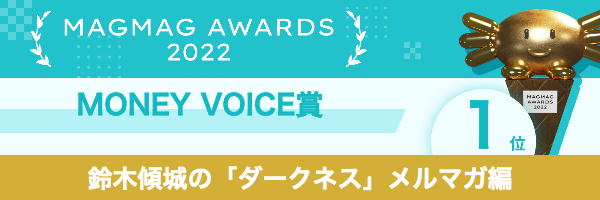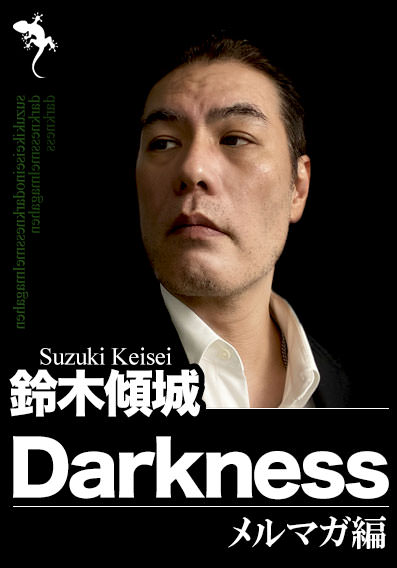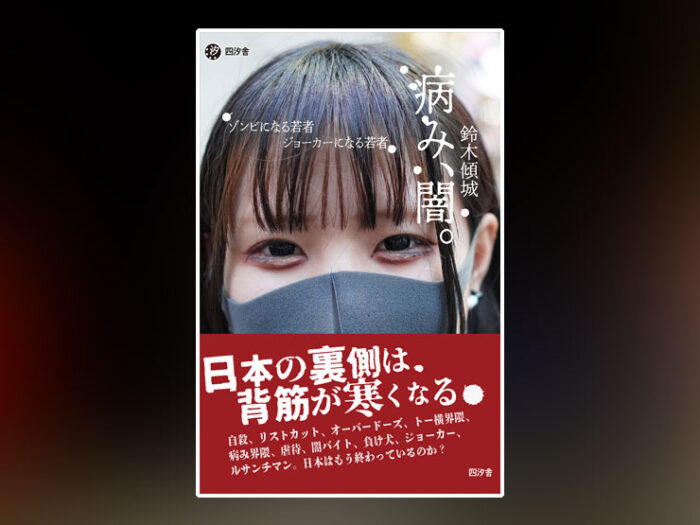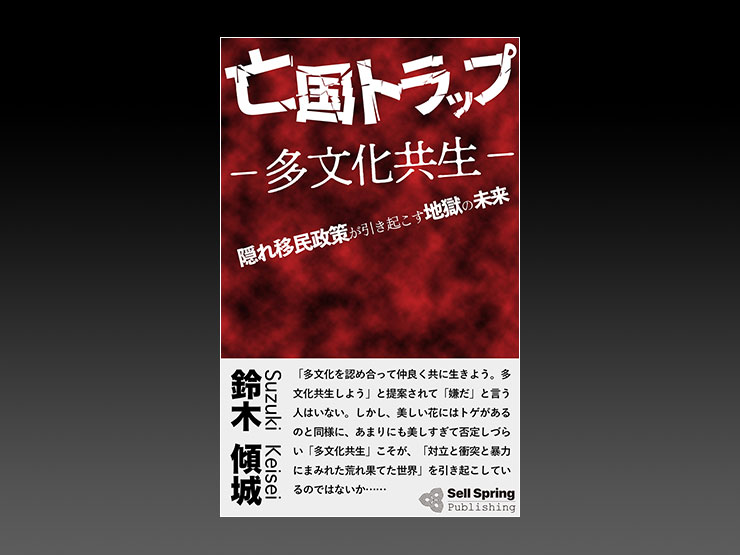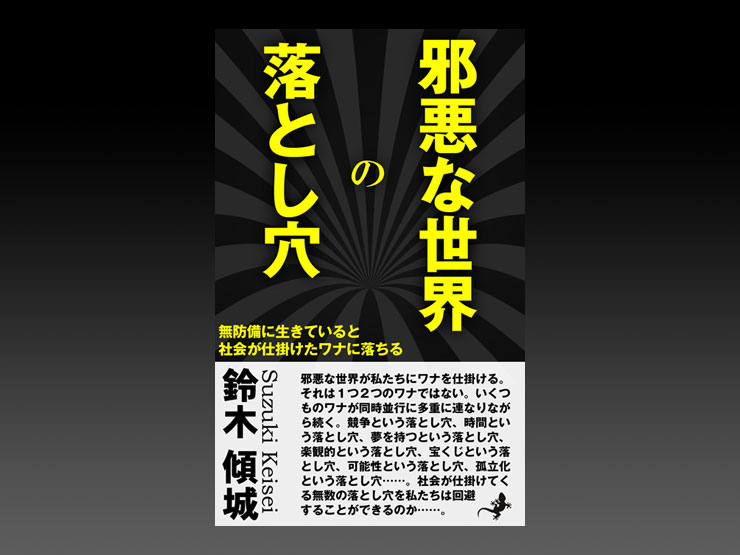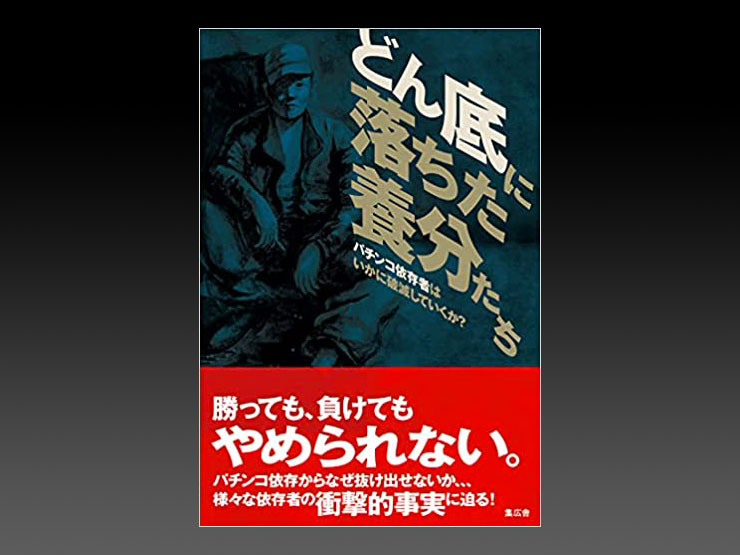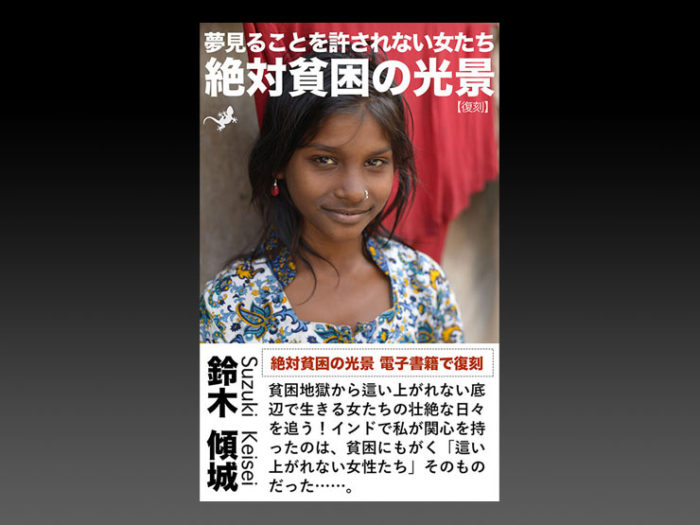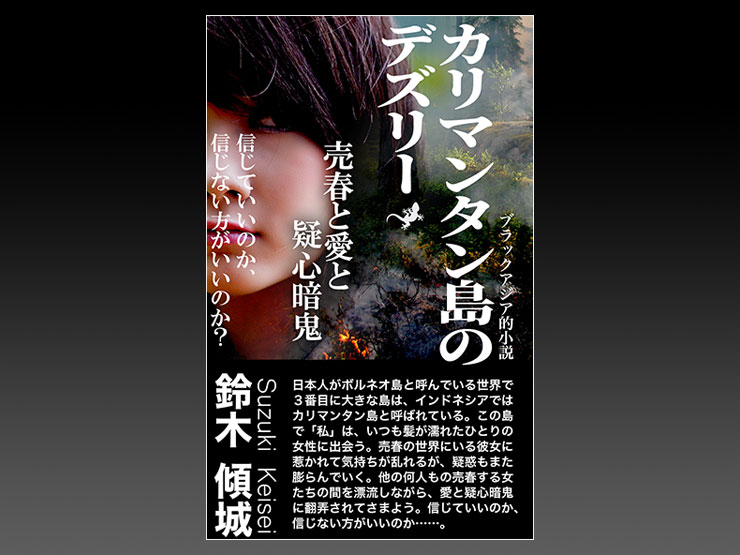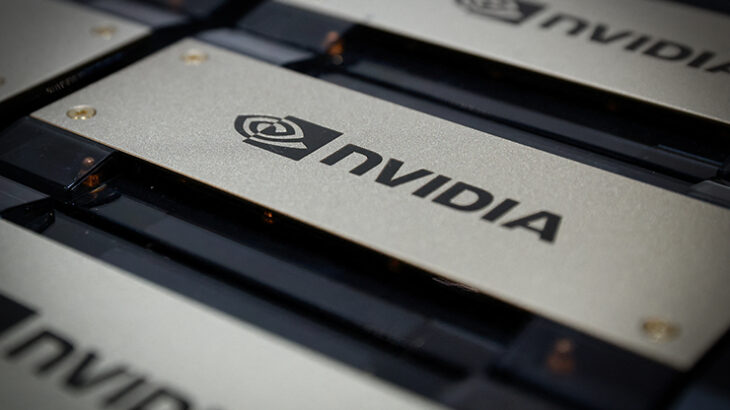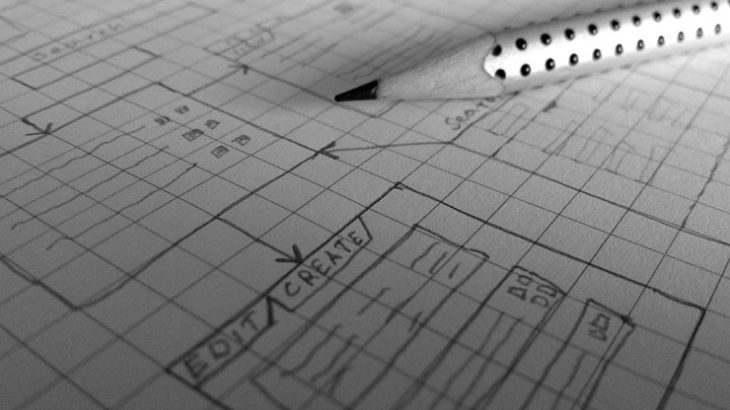今後、AIは私たちの仕事や日常の中心となっていき、これからの時代はもはやAIがなければ生きていけないような社会になっていくだろう。ほとんどの人はまだ気づいていないが、今この瞬間、世界は「新しい次元に入った」のだ。今後、AIは私たちの仕事や日常の中心となっていく。(鈴木傾城)
プロフィール:鈴木傾城(すずき けいせい)
作家、アルファブロガー。まぐまぐ大賞2019メディア『マネーボイス賞』1位。政治・経済分野に精通し、様々な事件や事象を取りあげるブログ「ダークネス」、アジアの闇をテーマにしたブログ「ブラックアジア」、投資をテーマにしたブログ「フルインベスト」を運営している。「鈴木傾城のダークネス・メルマガ編」を発行、マネーボイスにも寄稿している。(連絡先:bllackz@gmail.com)
もうそのSFの世界が私たちの目の前に現れていた
2024年5月。アメリカの株式市場が上昇し、S&P500が5300ドルを超えている。過去最高値である。その背景に何があるのかというと、急激に立ち上がって世界を席巻している生成AIの凄まじい進化である。
2024年5月16日、OpneAIは新AIモデル「GPT-4o」を発表しているのだが、その内容は世界を驚かせるに十分なものであった。ChatGPTは、まるで生きている人間のように会話をすることができるようになっていた。
対話の中で、冗談を言うこともできるし、声のトーンを感情的にすることもできるし、機械的にすることもできるし、さらに歌うことできるようになっていた。スマートフォンのカメラで数学を見せると、その説き方を人間に解説することもできるし、外国語を翻訳することもできた。
これを見て、多くの人が10年前の映画『her/世界でひとつの彼女』のサマンサを思い出すと感想を述べた。この映画は人工知能OS「サマンサ」と恋する男の物語だったのだが、10年前は「こんなことはあり得ない」と誰もが思っていたが、もうそのSFの世界が私たちの目の前に現れていたのだ。
恐るべきテクノロジーの進化である。その「GPT-4o」の発表があったあと、今度はグーグルもまた負けじと自社AIのGeminiの進化を発表している。今後は、アップルも、アマゾンも、メタも、アドビも、オラクルも、そしていくつもの新興企業が次々と驚くべきAIを発表してくるだろう。
おおよそ、現代人でアメリカのハイテク企業の製品やサービスを使わずに日常生活を送れる人はほとんどいなくなっている。Microsoftも、Adobeも、Netflixも、まるで当たり前かのように全世界対応のサービスを行っている。
Adobeは一般の人にはあまり知られていない企業だが、この企業の製品であるフォトショップ、イラストレーター、インデザイン等のソフトウェアが使えなくなると、印刷業界は一瞬にして壊滅してしまうほど業界を独占しているのだ。
【金融・経済・投資】鈴木傾城が発行する「ダークネス・メルマガ編」はこちら(初月無料)
米IT企業が終焉などと言っていると嘲笑される
今、私たちの文明はテクノロジーがなければ何も始まらない世界になっているのだが、その根幹の部分をアメリカのハイテク企業ががっちりとつかんでいて、代替品はどこにもない。
WindowsやMac、iPhoneやAndroid、こうしたOSや機器がなくなってしまったら、私たちは仕事や日常生活を送ることができない。
アメリカのハイテク企業がいかに凄まじいのか、それを考えるだけでも分かるはずだ。気がつかなければならないのは、こうした巨大な分野で熾烈な争いを繰り広げて技術独占するのは、すべてアメリカのIT企業だという現実である。
世界は自由競争の時代なのだから、どこの国のどこの企業が競争に打ち勝って世界制覇してもおかしくない。しかし、今のところ、そのスケール感や技術的なイノベーション(革新)では、アメリカのIT企業に太刀打ちできる他国の企業が存在しない。
全世界のイノベーションは、今後もアメリカのハイテク企業が牽引し、数十年に渡ってリードしていくのは確実になっている。
他国のIT企業がアメリカのIT企業による技術独占を阻止しようと思っても、あるいはビジネスモデルを真似しようと思っても、規模的にも技術的にも敵わないので追いつくことすらもできない。
したがって、今後もアメリカのハイテク企業がイノベーションと独占を確保していくのは間違いない。そして、AIだけでなく「次世代のイノベーション」も間違いなくアメリカのハイテク企業が独占していくだろう。
そういえば、「アメリカは終わった、アメリカは凋落した、アメリカのハイテク企業も終わりだ」と、10年以上も前から馬鹿のひとつ覚えのように言っているアナリストもいたのだが本当に愚かだ。
アメリカのハイテク企業は成長が終焉するのではなく、むしろこれからも相変わらず凄まじいイノベーションを引き起こしながら成長していく現実がまったく見えていない。
終焉どころか、これからだ。アメリカのハイテク企業が持つその潜在能力は、まだすべて見えていない。
【ここでしか読めない!】『鈴木傾城の「ダークネス」メルマガ編』のバックナンバーの購入はこちらから。
今この瞬間、世界は「新しい次元に入った」のだ
あらゆるモノがインターネットにつながり、その無限大のビッグデータを瞬時に解析する「能力」がアメリカのハイテク企業にはある。インターネットのデータの集積地はクラウドであり、そのクラウドもまたアメリカのハイテク企業がほとんどを担っている。
そして、そのビッグデータがAIの知識の源泉になる。
グーグルのCEOサンダー・ピチャイ氏は2016年の段階で「今後は人工知能ファーストに移行する」と宣言していた人物だが、2023年になってOpenAIが開いた怒濤のようなイノベーションを見ると、一気呵成に勝負に打って出ている。
サンダー・ピチャイCEOは「AIがインターネットやモバイルをしのぐ勢いで成長している」と述べているのだが、私たちは今まさにその時代の転換点のまっただ中にいて、世界が変わる瞬間を見ている。
今後、AIは私たちの仕事や日常の中心となっていき、これからの時代はもはやAIがなければ生きていけないような社会になっていくだろう。
ほとんどの人はまだ気づいていないが、今この瞬間、世界は「新しい次元に入った」のだ。
ここから、ロボット技術、無人運転、ウェアラブル機器、ドローンに関して、すべてがAIにリンクして今までの次元を超えていくのだ。
また、人工知能は私たちがまだ想像したことがないような新しい製品を莫大に生み出す可能性も秘めている。
こうした状況を冷静に確認すると、アメリカのハイテク企業は、一過性ではなく、今後も世界を揺さぶる凄まじい潜在能力を秘めた業界として君臨していく未来が見えてくるはずだ。
ダークネスの電子書籍版!『邪悪な世界の落とし穴: 無防備に生きていると社会が仕掛けたワナに落ちる=鈴木傾城』
イノベーションは、終わりどころかむしろ始まりである
アメリカのハイテク企業は既存のITビジネスからさらに一歩先のイノベーションに突入した。アメリカ社会はそれをどんどん受け入れて、社会そのものを一気に変えていく。
日本では政治家や官僚が何でもかんでも規制して、結果的に社会を停滞させてしまう社会なのだが、アメリカはまったく違う。
イノベーション・ファーストの文化があり、新しいアイデアを持った企業を次々と上場させる土壌もあり、チャレンジを尊ぶ気質もある。このすべてが合わさって次世代の世界を作り上げる。
インターネット業界の成長は、ひとつのイノベーションが起きるとそれが全世界を独占するまで続き、それが一段落するとまたスマートフォンのイノベーションが核になって、それが全世界を独占するまで成長が続いていった。
そして、今度はAIでイノベーションを切り拓いて全世界を独占しようと動き出している。
しかも、その「次のイノベーション」は山ほど待っている。ロボットも、無人運転も、空間コンピューティングも、ドローンも、とにかくイノベーションが目白押しなのだ。
ひとつの大きな波が落ち着いても、それで終わりということにならない。終わりどころか、むしろ次の始まりであると捉えなければならない。
アメリカのハイテク企業の潜在的な能力は計り知れない。さらに、今後は「まだ私たちが知らない米ハイテク企業」も、急激な勢いで巨大化していく可能性も秘めている。
「アメリカが終わる」と10年以上も前から言っている人や、「次の時代は中国だ」といまだに言っている人や、少しアメリカの株価が下がると「終焉だ、破滅だ」と言い出す人がいるが、彼らは現実が見えていない。
アメリカのイノベーションを生み出す能力は、まったく衰えていない。恐ろしいほどだ。次にやってくる「新しい波」もまたアメリカが制する。アメリカの超巨大IT企業の次の成長力を見くびったら、激動の時代に出遅れる。